|
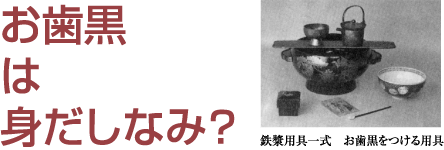 |
お歯黒は「鉄漿[かね]」ともいい、婦女が歯を黒く染めた風習です。一説によれば日本のお歯黒の風習は古墳時代(紀元2〜3世紀頃)からはじまったと言われ、その頃の埴輪[はにわ]のなかにお歯黒をしたものが見受けられます。日常の風習となったのは平安時代になってからのことで、平安中期になると、女性だけでなく男性もするようになりました。そのきっかけは、後三条天皇の時代(1068〜1072)のひとりのキザな公卿[くげ](源有二)の気まぐれからだと言われています。その公卿は、自分の顔を女性のように柔和[にゅうわ]に見せるためにお歯黒をしました。それ以降、女性の関心をひこうとして男もお歯黒をする習慣ができました。そして、平氏が公卿のまねをし、武士も歯を黒く染めるようになりました。「女の歯を染めるは必ず婚談定まりてのことなり、黒色は変亡せざる故、夫婦の間も変はるまじりとの義なり」と記されていて、武士は、忠臣二君に仕えず、という心意気を、女性は貞節[ていせつ]すなわち二夫にまみえず、という大切な誓いの意味をもっていたのです。
お歯黒の有名な話に、『新平家物語・ 巻9』(吉川英治)に書かれた平敦盛[たいらのあつもり]の最後の場面があります。熾烈[しれつ]をきわめた一の谷の戦いも、暮色[ぼしょく]とともに平家の敗北が決定的となります。源氏方の熊谷次郎直実[くまがいじろうなおざね]が、落ちのびていく敦盛を波打ちぎわに見つけ、力にまさる直実が敦盛を組みふせて、首をかかんと内兜[うちかぶと]を持ちあげてみると、年の頃は16〜17歳、自分の子どもと同じくらいの若大将であることがわかります。「黒々と歯に鉄漿を染め、薄っすらと、公達[きんだち]化粧の痕を残し、覚悟の眉をひそめている様、何かあどけなくさえ思われた。生きながら死んでいる乙女の容顔[かんばせ]を見るかのような心地がした」、直実は泣く泣く敦盛の首に刀を入れたとあります。 巻9』(吉川英治)に書かれた平敦盛[たいらのあつもり]の最後の場面があります。熾烈[しれつ]をきわめた一の谷の戦いも、暮色[ぼしょく]とともに平家の敗北が決定的となります。源氏方の熊谷次郎直実[くまがいじろうなおざね]が、落ちのびていく敦盛を波打ちぎわに見つけ、力にまさる直実が敦盛を組みふせて、首をかかんと内兜[うちかぶと]を持ちあげてみると、年の頃は16〜17歳、自分の子どもと同じくらいの若大将であることがわかります。「黒々と歯に鉄漿を染め、薄っすらと、公達[きんだち]化粧の痕を残し、覚悟の眉をひそめている様、何かあどけなくさえ思われた。生きながら死んでいる乙女の容顔[かんばせ]を見るかのような心地がした」、直実は泣く泣く敦盛の首に刀を入れたとあります。
『北条五大記』にも、昔、関東の敵味方の合戦の時に、首実検でお歯黒をした首を武士の首と言って見せたので、戦場で討死[うちじに]することを覚悟して、もし討死した時には恥をかかないようにと、楊枝[ようじ]でお歯黒をするよう心がけていたと書かれています。しかし、戦国末期には、鉄砲を導入したスピードのある戦いとなったため、お歯黒をする余裕もなくなり、武士のお歯黒は姿を消していきます。
 一方、女性のお歯黒はますますさかんになり、お歯黒をしない女性は女性ではないとまで言われるようになります。幕末になるとしばしば異人が来航するようになり、彼らにはお歯黒は異様なもの、醜いものと映ったらしく、アメリカ艦隊のペリー提督は『日本遠征記』のなかで、「彼女らがつつましくほほえむとルビーの唇が開いて、恐ろしげな腐蝕[ふしょく]した歯ぐきに真っ黒な歯が並んでいるのがニュッとあらわれた」と、グロテスクな奇習[きしゅう]として紹介しています。 一方、女性のお歯黒はますますさかんになり、お歯黒をしない女性は女性ではないとまで言われるようになります。幕末になるとしばしば異人が来航するようになり、彼らにはお歯黒は異様なもの、醜いものと映ったらしく、アメリカ艦隊のペリー提督は『日本遠征記』のなかで、「彼女らがつつましくほほえむとルビーの唇が開いて、恐ろしげな腐蝕[ふしょく]した歯ぐきに真っ黒な歯が並んでいるのがニュッとあらわれた」と、グロテスクな奇習[きしゅう]として紹介しています。
日本の社会に深く浸透したお歯黒が姿を消すのは、明治になってからです。明治元年と3年に、お歯黒をするのは古い制度に従うものであるから、中止すべきであるという禁止令を政府が出すのですが、庶民はなかなかお歯黒の風習をやめようとはしませんでした。そこで、明治6年、皇后と皇太后が自らすすんでお歯黒をやめて模範を示し、それから以後、お歯黒の風習は急速に姿を消していったのです。しかし、皮肉なことにこのお歯黒が、むし歯予防に非常に有効なことがわかってきたのです。 |
出典
磯村 寿賀人
『おもしろい歯のはなし 60話』 大月書店 |
|
|