|
|
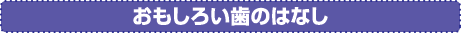 |
 |

シュメール人の教典(虫の伝説) |
むし歯の痛みは、いつの世においても耐えがたい苦痛であったことは想像に難しくありません。古代の人々にとっては、その原因がまったくわからないのですから、不安を通りこして得体の知れない不気味な現象であったことでしょう。どうしたらむし歯が防げるか、口腔衛生のめばえとともに口の中を清潔にすればよいという対症療法的な知識はあっても、なぜむし歯ができるのかは、理解の範囲を越えるものでした。原因に関するもっとも古い記述は、中国は殷の時代(BC1500年頃)の甲骨文字に、「王の歯を疾めるは、これ虫なるか、これ虫ならざるか」という意味のことが書かれています。西洋では、BC5000年頃に書かれたメソポタミアのシュメール人の教典に見ることができます。「虫の伝説」と題し、神の呪文を唱えれば歯を害する虫を殺すことができると記されています。 古代においては、口の中に目に見えない虫がいて、それが歯をくさらすのだと考えられていたようです。ギリシャの医学の父といわれるヒポクラテス(BC460、450〜370年)は、それまでの医術が呪術や魔法の域を出なかったのを、健康と病気を科学的に観察し、体系的にまとめています。彼は、歯痛は「粘液が歯の根に蓄積して起こる」とし、悪液が歯の中にたまったために発生すると考えていました。アリストテレス(BC348〜322年)はいちじくを食べるとその実が歯にくっついて腐敗し、そのままにしておくと歯を破壊するとしています。 古代においては、口の中に目に見えない虫がいて、それが歯をくさらすのだと考えられていたようです。ギリシャの医学の父といわれるヒポクラテス(BC460、450〜370年)は、それまでの医術が呪術や魔法の域を出なかったのを、健康と病気を科学的に観察し、体系的にまとめています。彼は、歯痛は「粘液が歯の根に蓄積して起こる」とし、悪液が歯の中にたまったために発生すると考えていました。アリストテレス(BC348〜322年)はいちじくを食べるとその実が歯にくっついて腐敗し、そのままにしておくと歯を破壊するとしています。
口の中にむし歯を作る見えない何かが存在するということは、誰しも漠然と考えていたようですが、はっきりととらえられるにはルネサンスまで待たねばなりませんでした。
オランダの博物学者レーウェンフーク(1632〜1723)は、レンズみがきの技術や金属を細工する技術を覚えて顕微鏡を作り、ひとりで微細なものを根気よく観察して楽しんでいました。あるとき自分の歯の表面にくっついている食べかすを観察していて、何やら動めく小生物を発見したのです。そして、イギリスのロンドンにあるロイヤル・ソサエティに「むし歯の歯から採取した小さな虫が、とかく歯の痛みを起こす」と報告したのです。ようやくにして、むし歯の虫の実体が目でとらえられたのです。
 一方、日本ではむし歯のむしが何であるかはわかりませんでした。口の中に虫のようなものがいるようだし、歯ぐきが痛んで腫れてきて「あご」の周囲が蒸すようになるので、「蒸し歯」だという説を唱える者もありました。治療もまじないの域を出ず、むし歯の痛みを止めるのに「急急如律令」と紙に書いて噛みしめれば治るとか、霊験あらたかな絵馬を奉納するとか、民間療法的な治療法がまだ行われていたのです。日本にはじめて西洋の歯科治療法をもたらしたのは、1823年に長崎の出島に来日したドイツ人医師シーボルトだと言われています。 一方、日本ではむし歯のむしが何であるかはわかりませんでした。口の中に虫のようなものがいるようだし、歯ぐきが痛んで腫れてきて「あご」の周囲が蒸すようになるので、「蒸し歯」だという説を唱える者もありました。治療もまじないの域を出ず、むし歯の痛みを止めるのに「急急如律令」と紙に書いて噛みしめれば治るとか、霊験あらたかな絵馬を奉納するとか、民間療法的な治療法がまだ行われていたのです。日本にはじめて西洋の歯科治療法をもたらしたのは、1823年に長崎の出島に来日したドイツ人医師シーボルトだと言われています。
近代的なむし歯の病因の探究のさきがけとなったのは、1835年にロバートソンが歯にくっついた食物の残りカスから、発酵によって酸が生じるのではないかという疑念を抱いたのがきっかけで、口の中で作り出される酸によって歯が溶かされることがむし歯の原因ではないかと考えられるにいたったのです。1889年アメリカのW・D・ミラーが有名な化学細菌説を発表し、飛躍的に研究が進むことになりました。
出典
磯村 寿賀人
『おもしろい歯のはなし 60話』 大月書店 |
|
|