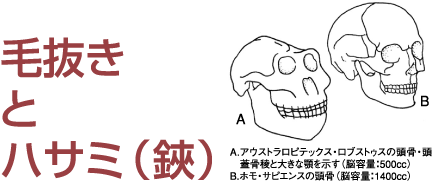 |
人間は、北上を続けながら寒さに適応してゆきました。吸いこんだ冷たい大気が肺を痛めないように、鼻の奥に空洞のような洞穴が大きく形づくられました。高く隆起した鼻の奥の洞穴で、冷たい空気が暖められました。そのために、頭に接している鼻の付近の骨の退化の早さは、下のあごほど早くはありませんでした。
猿人や原人たちの顔の中で鼻から下の咀嚼器官を見てみますと、頭の骨全体の半分近くを占めるほどの大きさを持っています。そして、上のあごと下のあごが同じくらいの大きさであることがわかります。彼らは硬い食べものを食いちぎったり、噛み砕いたりしなければならないために、がんじょうな咀嚼器官を持たなければならなかったのです。ですから、上の歯と下の歯とはぴったりすきまがないようにかみ合わされていました。つまり、たとえれば、馬蹄形(ばていけい)のアーチを持ったふたつの同じ形のものを、上下に重ね合わせていたのです。彼らはハサミやナイフなど持ち合わせていませんでしたから、前歯で引きちぎり、臼(うす)ですりつぶすようにして食べものを食べていました。そして、火の発見や柔らかい食べものを利用することを覚えてから、急速に上のあごと下のあごの退化、退縮化が進みました。上のあごの骨よりも、下のあご骨のほうが早く小さくなりましたので、噛み合わせ、つまり上下の馬蹄形のアーチに食い違いが生じるようになりました。上のあごと下のあごを噛み合わせると、下のあごが上のあごの内側に入りこんでしまう形となったのです。
歯科的な専門用語で言いますと、猿人・原人たちは毛抜き状咬合と言い、毛を抜く器具のようにふたつの刃先がぴったりとくっつきます。 |
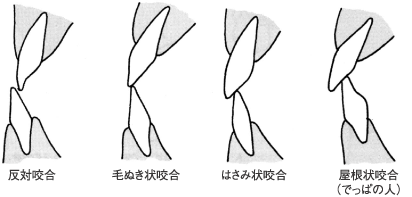 |
いっぽう、現代人は鋏状咬合といって、鋏のようにふたつの刃先がすれちがうようになっています。言うなれば、毛抜き状咬合は食べものを引きちぎり、鋏状咬合は切りとるような形式になっています。古代の人たちは毛抜き状咬合で、日本人で言いますと、狩猟採集生活を送っていた縄文時代の人々はすべて毛抜き状咬合でした。
しかし、弥生時代に入って稲作が普及しますと、鋏状咬合があらわれはじめ、古墳時代には、四分の一に鋏状咬合が見られるようになります。稲作が普及し、食生活が豊かになるにつれ、鋏状咬合が増え、穀物栽培が盛んになって穀類が主食となる鎌倉時代に逆転現象が起きますが、以後鋏状咬合が増え続けていきます。
このような咬合がすすみ、上の歯が前方に傾斜して、下の歯が上の歯の歯茎近くにまで後退して咬み合うようになるのを屋根状咬合といい、いわゆる出っ歯といわれる形になります。稲作文化の先進国の日本人には古来からこの屋根状咬合が多く見られ、中世から来日した外国人たちは日本人の印象を、背が低く、出っ歯が多いと書き記しているほどです。鋏状咬合が増えるということは、それだけあごの骨が小さくなってくるということであり、古墳時代以降から不正な咬み合わせや歯ならびの悪い人が、右肩上がりに現代まで増えつづけてきました。 |
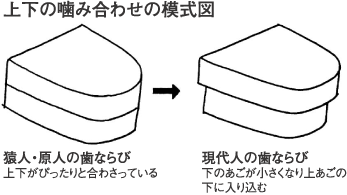 |
出典
磯村 寿賀人
『おもしろい歯のはなし 60話』 大月書店 |